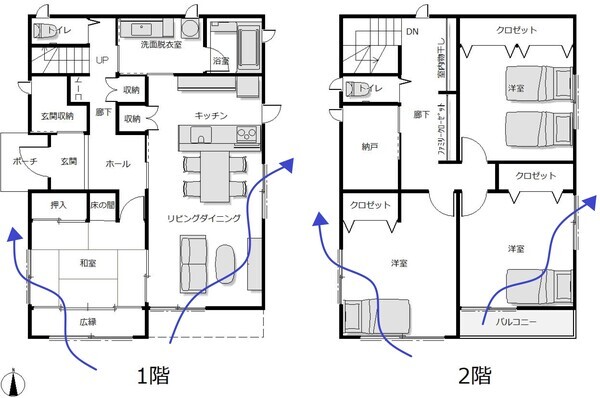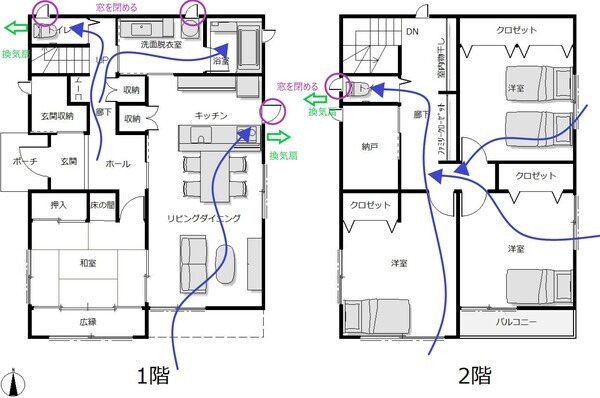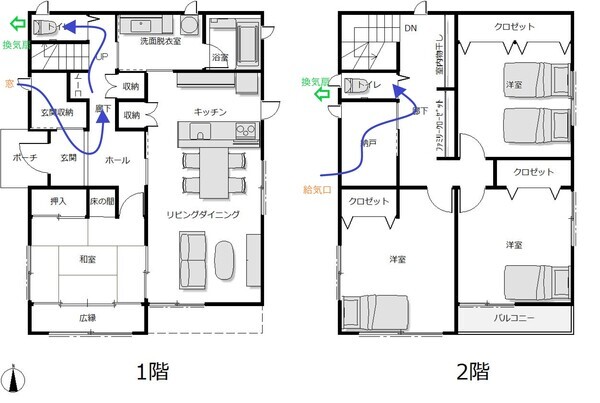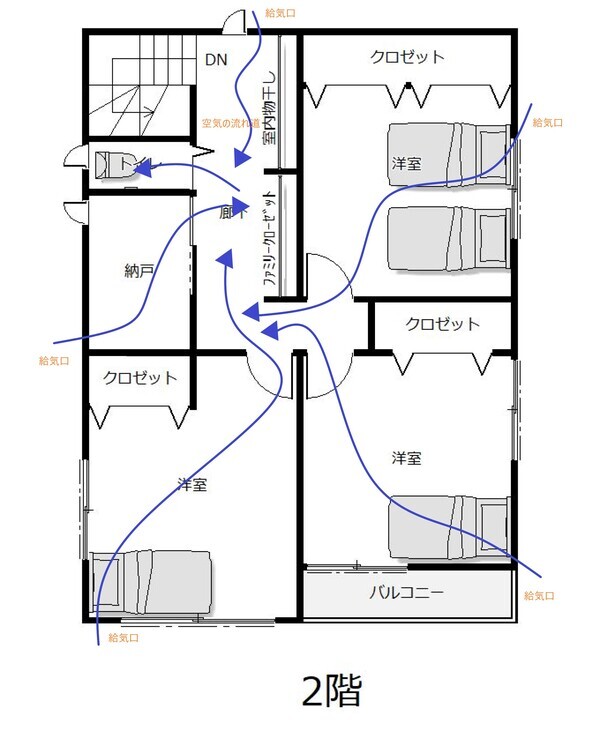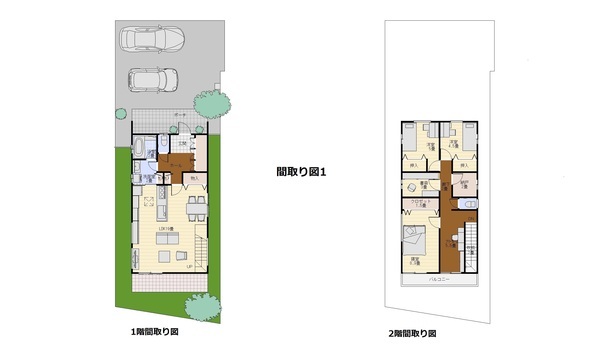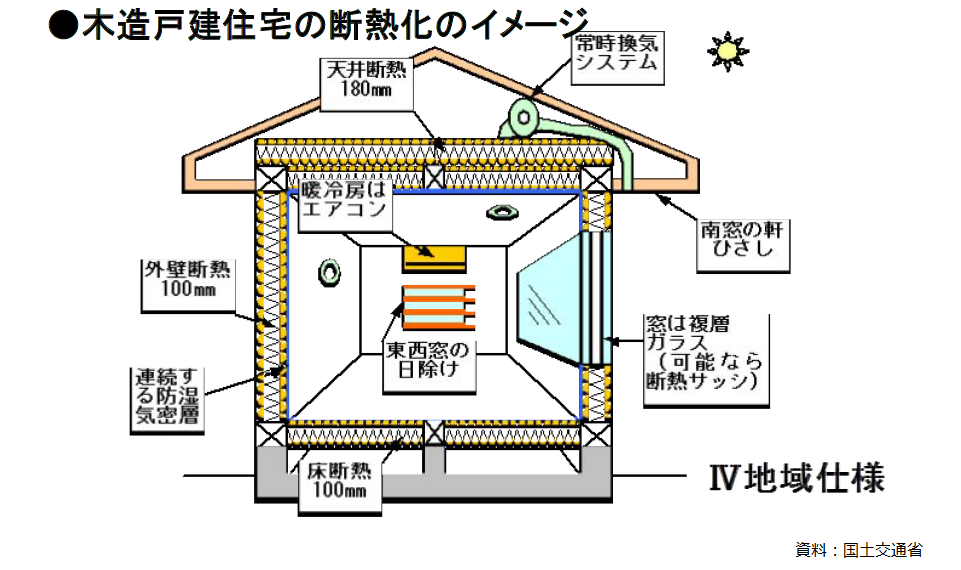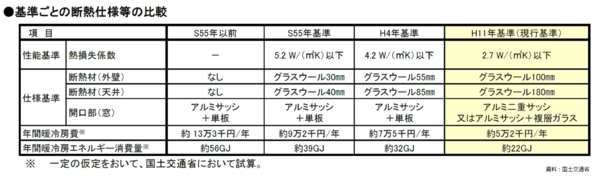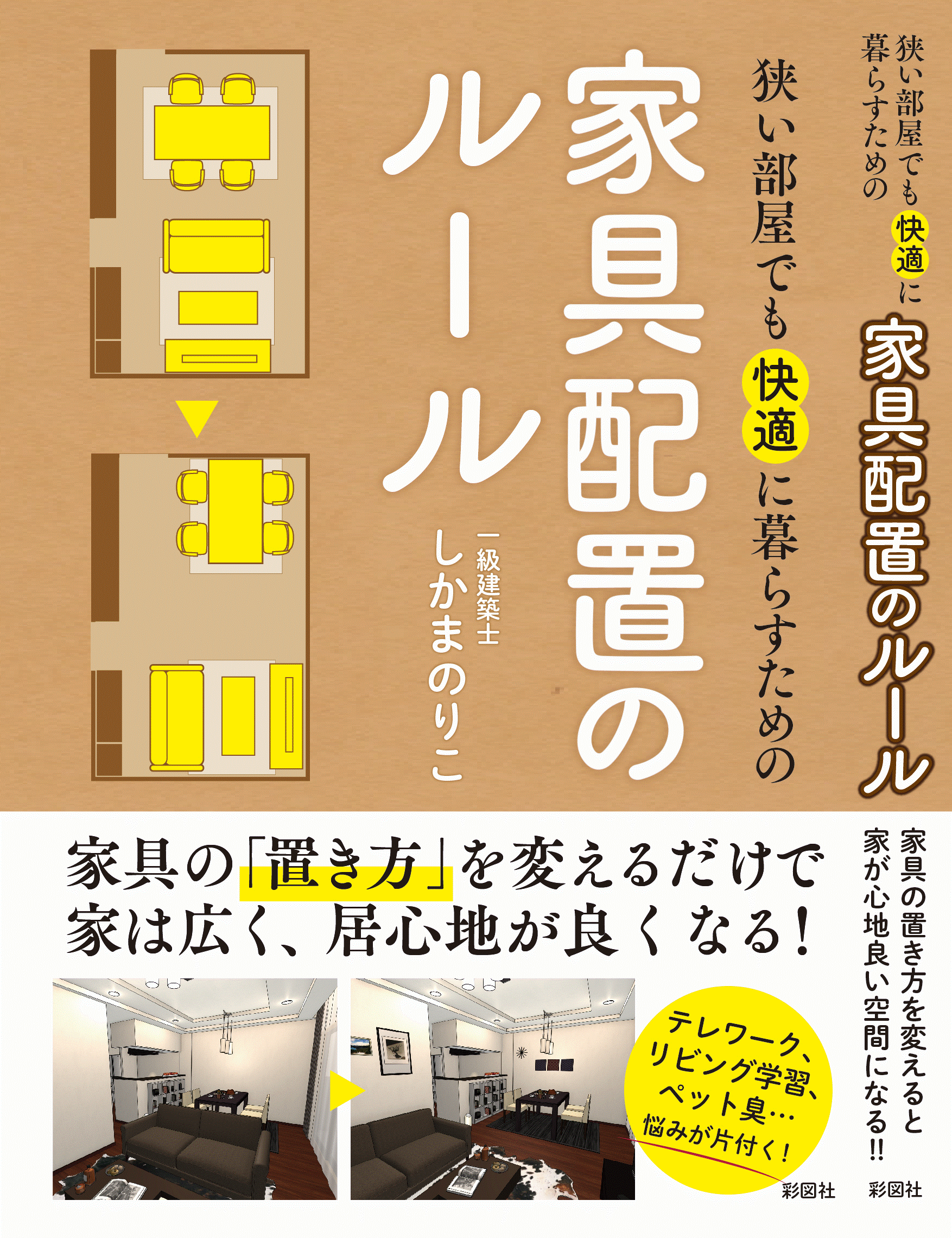収納付きダイニングテーブル ~millefeuille ミルフィーユ~

どんどん片付く魔法のダイニングテーブル新発売!
ダイニングテーブルが「物置」状態になっていませんか?
「ああ~そうそう・・・」とへこまれた方
ご安心くださいませ、みなさまほぼ同じ状態です。。
部屋づくりや家具配置相談をしてますと、
子育て世代に限らず多くの方がモノであふれたリビングダイニングにヘキヘキしていらっしゃいます。
モノが散らかる原因としてはモノが多すぎることも一つの要因ですが
同じく収納が少ないことも挙げられます。
しかしリビングダイニングという家具られたスペースに容易に家具は増やせませんよね?
そこで開発されたのが、、、
収納付きダイニングテーブル
millefeuille ミルフィーユ
~ Designed with Function ~
名前の通り、ダイニングテーブルに大容量の収納機能が付いたものです。
今までのダイニングテーブルは収納がないものがスタンダードでしたが、
ミルフィーユはカラーボックス2個分の収納量があります。
眼鏡・薬・血圧計・A4ファイル・雑誌・新聞・ノートパソコン・お箸などのカトラリー・布巾・TVやエアコンのリモコン・ティッシュケースはもちろん
テーブルサイドに引っ掛け棒があるので、コロコロなどの掃除用品も下げられますし、トートバッグやランドセルもかけられます。
すごくないですか?
このテーブルがあればテーブルの上はいつも片付いた状態でいられますね!!つまりお部屋がどんどん片づくんです♡
このテーブルは「ゆりかごから墓場まで・・・?」ではありませんが赤ちゃんからお年寄りまで
一生使えるように丈夫な無垢材でできています。また自然素材にこだわり植物オイルで仕上げており環境にも配慮したテーブルになっています。
国内の工場で一つ一つ丁寧につくられる完全受注生産品です。
また私の家具配置アドバイス付きですので
「きちんと配置できるかしら?」
「今使っている椅子はそのままテーブルだけ買い替えたいけれど、イスにサイズが合うかしら?」
などの不安がある方もご安心くださいませ。責任をもってアドバイスさせて頂きます。
「ミルフィーユ」はお菓子の名前に由来しています。
~テーブルを囲む家族がお菓子を食べた時のように笑顔になるように~という思いでデザイン作成し名付けたものです。
販売価格は25万円(税抜き)※プロによる家具配置アドバイス付き
ダイニングテーブルの買い替えはもちろん
出産祝いや新築祝いにいかがでしょうか?
皆様のご注文お待ちしております。ご注文はこちらから